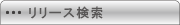現在ご利用頂いております「VFリリース」につきまして、ユーザビリティの向上、機能追加、品質向上を目的とし、2012年4月1日(日)に「ValuePress!」と配信サービスを統合させて頂く運びとなりました。
配信サービス統合に関する
詳細はこちらをご覧下さい。
(2012-03-19 00:00:00)
クラシックコミュニケーション株式会社は、株式会社バリュープレスと平成24年3月1日付けでPR総合支援企業に向けた経営統合を行うことを決定致しました。
詳細は
こちらをご覧下さい。
(2012-02-28 12:00:00)